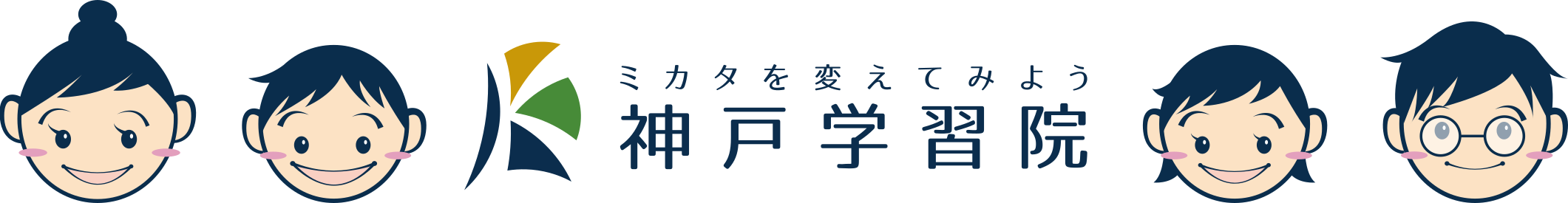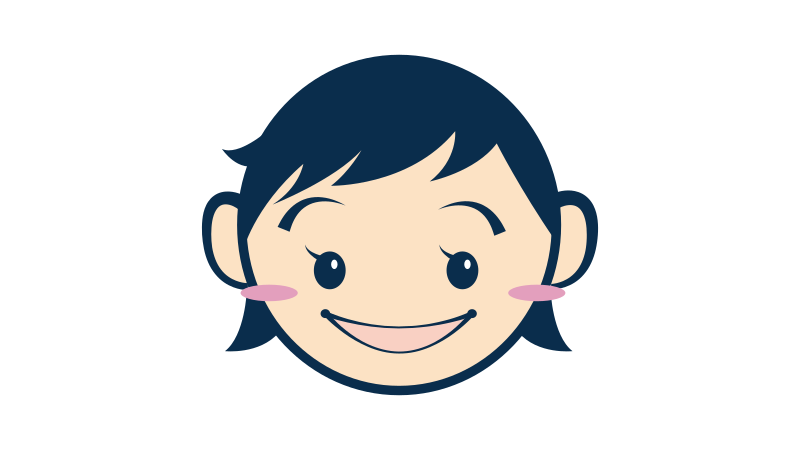先生、この証明見てもらえますか?
宿題でもないのに自分なりに証明を考えてきたのは、高校1年生のYちゃんです。数学の授業中に講師がした話に興味を持ったようで、いろいろ考えてきたようです。
そんな彼女の学習は、真剣そのものです。分からなくても、とにかく分かろうと必死でもがきます。どうしても分からなければ助けを求めてきますが、解説を聞いただけでは満足しません。さらにいろいろ考えて、本当に理解できたのかどうかを必ず自分なりに試そうとします。
また学習のアドバイスをよく聞き入れて、懸命に実践しようとしますし、授業の後にはいつも自習室で自習して帰ります。受験生でもないのに、自習室で何時間もぶっ通しで考え続けるような姿もしばしば見かけます。このように真剣に取り組むからか、大きな成果をあげつつあります。
彼女がこのように取り組むのは、自律的な動機づけが育っているからです。自律的な動機づけがしっかり育っている生徒は、彼女に限らず皆が懸命に学習に向き合います。決して手を抜いたり、言い訳をするようなことはしません。たとえ勉強が好きではなかったとしても、自身の学習に責任を持ち、懸命に向き合います。
では、彼女の自律的な動機づけが育くまれたのはなぜでしょうか。その最大の要因は、お母様の接し方にあると思います。お母様が彼女の自律性を大切にしておられることは、お話を伺うなかでよく伝わってきました。子どもの意欲を上手く育てられる親御様に共通するものを、Yちゃんのお母様もまた持っておられると感じました。
今は懸命に頑張るYちゃんですが、そんな彼女にもなかなか勉強に向き合えない時期が過去にあったそうです。低迷する成績に、お母様は大きな不安を感じられたそうです。ですが、あれこれ口出しして彼女を変えようとするのではなく、彼女がハマっているゲームで一緒に遊んだり、ボーカロイドの音楽に一緒にハマったりしながら、元気でいてくれるYちゃんをそのまま受け止められたそうです。
今のYちゃんが心から勉強に向き合えるのは、そんなお母様からの温かい支えがあったからに違いありません。